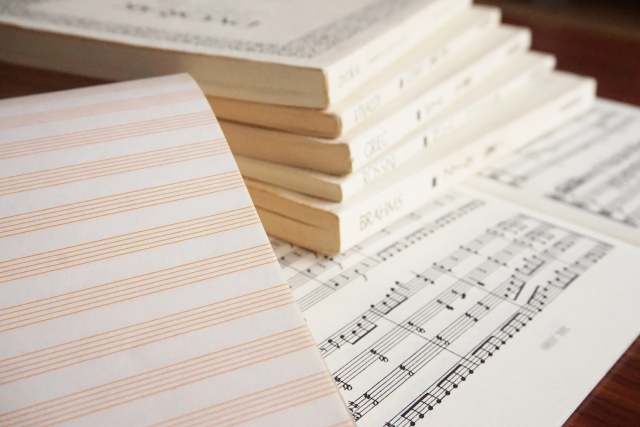演奏したり作曲したりするために必要な音楽の基礎知識、楽典。楽譜に書かれている音やリズムの読み方はもちろん、レベルが上がっていけば調性や音程、和音の種類、楽曲の形式、記号、奏法の意味なども理解する必要が生じてくるので、楽典の勉強をすることは必須となります。専門の道に進むわけではなくても楽典の知識を持っているとより音楽への理解が深まり、より楽しめるようになります。今回は楽典の勉強のためにお勧めの3冊をご紹介します。
定番の1冊 音大受験を考えている方に
こちらは音大受験をする人は必ず持っているといっても過言ではない超定番の本です。

私もこれで勉強しました
初版が1965年なのでもう60年近く出版され続けている本です。
音楽の理論について過不足なく端的に説明されています。(終止形についての説明はなぜか欠けているのですが)
ただ、音大を受験するなど専門的に音楽の道に進もうという人には
この本は実践問題もたくさん載っているし
これくらいまじめに硬く説明されている本がよいとは思うのですが
何せ日本語がとっつきにくい。
最初に挙げた割には実はこの本を私はあまり好きではない(苦笑)
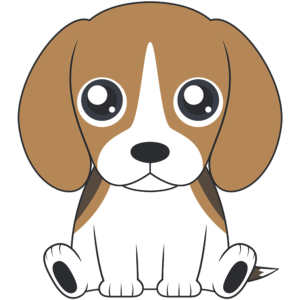
初めて楽典を勉強したいという人のためには次の本がおすすめらしいよ~。
わかりやすく楽しく勉強できる! 初めて楽典の勉強をしようと思う初心者の方に
カラフルで語り口もやさしくとても分かりやすいです。
音楽史やいろいろな楽器の説明も載っていたり
コードネームについての解説もあるので
クラシックだけでなくポピュラー音楽の勉強のためにもいいと思います。
付属のDVDも非常にわかりやすく
まったく楽譜の読めない私の旦那さんでも「よくわかる」と楽しんで見ていました。
(Kindle版にはDVDが付いていないのでご注意を。紙の書籍をお求めください。)

楽典の勉強のための最初の1冊として是非!
読み物としても面白い究極の一冊! 専門家、大人の音楽愛好家の方に
テレビでもおなじみの青島広志さんによる
「教科書でもありエッセイ集でもある」ような本です。
知識量も多く高度な内容ではありますが、読み物としても楽しく、
青島広志さんの作曲家、東京藝術大学講師としてのアカデミックな面と
テレビやコンサートなどでお見掛けするエンターテイナーとしての両面が文章から感じられ
専門家もアマチュア音楽家も音楽上の知的な喜びを得られる究極の一冊だと思います。

タイトルにたがわない素晴らしい楽典の本だと思うわ。

楽典の知識が増えると音楽をより深く理解することができるようになり
演奏すること、聴くことの喜びも大きくなります。
ぜひどれか一冊を手に取って勉強してくださいね!